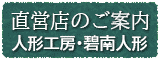鎧・具足と部位の名称
■大鎧(おおよろい)と当世具足(とうせいぐそく)
日本の鎧兜は、おおまかに大鎧と当世具足の2つに分類されます。
大鎧は、平安時代から続く伝統的な甲冑です。絵巻物に描かれる鎧兜はたいてい大鎧です。
当世具足は、室町時代後期から安土桃山時代にかけて出現したものです。技術の進歩、戦法の変化や西洋甲冑の影響などにより、発展しました。戦国時代の鎧兜といえばこのタイプの物です。
「当世」は当時の人たちが「現代式・現代風」の意味で名付けた名称です。
■鎧の部位と名称
- 鍬形(くわがた)
- 鍬形台(くわがただい)
- 吹返し(ふきかえし)
- 眉庇(まびさし)
- 面頬(めんぼう)
- 忍緒(しのびお)
- 大袖(おおそで)
- 胴(どう)
- 胸板(むないた)または
栴檀板(せんだんのいた)- 鳩尾板(きゅうびのいた)
- 籠手(こて)
- 手甲(てっこう)
- 草摺(くさずり)
- 佩楯(はいたて)
- 脛当(すねあて)
- 毛沓(けぐつ)