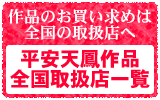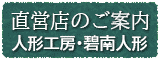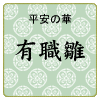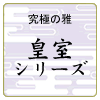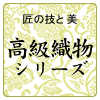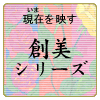お歯黒
鉄漿ともいいます。平安時代には貴族・武士の男性も施していました。 室町時代以降広まり、江戸時代になると結婚した成人女性は眉を剃り、お歯黒をする習慣が一般化しました。 明治に入り禁止令が出され、ちょんまげなどと一緒に日本人の習慣から消えていく事になります。 |
島台(しまだい)
京式の三人官女で中央の女官がもつ飾り。 州浜を形どった台の上に松竹梅、鶴亀等を配置した婚礼や饗応用の飾りです。 |
天鳳堂は人形師・平安天鳳作
手作り雛人形の製造元です
三人官女のおはなし
■比較的新しい官女人形
「ひな祭りの歴史」でも説明しましたが、段飾りというのは江戸時代後期以降に出現したものですので、段飾りを華々しく飾る三人官女も歴史的には比較的新しいものになります。
三人官女の形式そのものは何通りもあって、両端が立って中央が座る形、あるいはその反対、または三人とも立っているものもあります。

そもそも官女の数も三人と限らず、五人官女、七人官女も存在したようです。
■三人官女の構成
三人官女の場合、中央には眉を剃った既婚婦人で、口の中が黒く塗られているのはお歯黒をしているためです。ほかの2人は未婚で眉がそのまま、お歯黒もしていないというのが基本です。
■三人官女の持ち物
三人官女の持ち物は、長柄銚子、加銚子、盃(三宝)が一般的ですが、京式は盃でなく島台を持ちます。
平安天鳳作「釆女」と「公家正装官女」は持ち物が全く異なります。天皇に近侍する女官ということで持ち物の構成を昆布巻、鯛、かまぼこに変えています。
また、普通は官女の頭には特別な飾りはありませんが、公家の女性や上級女官の身分になると、おひなさまと同じように玉串をつけることがあります。
【参考】製品情報・三人官女